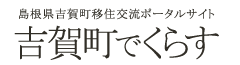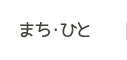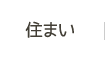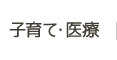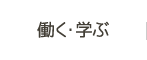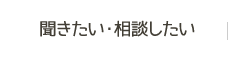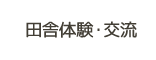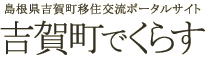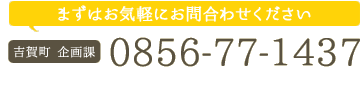よしかの農業
吉賀町は、面積の90%以上が山林の自然豊かな中山間地です。大きい面積の広い農地は少なく、山を切り開いてできた畑が各家の周囲を中心に広がっています。標高は250〜700mと集落によって差があり、土地によって若干産物も変わってきます。雨量が年間1,900ミリ前後と多く、夏は多湿・冬は冷涼で積雪も少なくありません。
昭和50年頃までは、農林業を中心とした第1次産業が基幹産業だった吉賀町。農業は稲作が中心で、田んぼを耕す為に牛を飼っている家庭も多く、雪の多い冬場は農業の合間に山陽圏へ出稼ぎにいくことで収入を得ていた農家もありました。
林業は木材生産のほか、炭焼き、紙の原料となるミツマタの栽培、養蚕なども盛んでした。中山間地の気候や地形、清涼な水等を活かし、ワサビや椎茸、栗といった特用林産物の生産は今でも盛んに行われています。また、今では生産農家が少なくなってしまいましたが、石州りんごと呼ばれる酸っぱいリンゴも栽培されています。
時代の変遷と共に、第2次産業・第3次産業へと就業形態がシフトし、農林業は従事者数・生産額共に減少してきてしまいました。農家・林家の高齢化も進んでおり、農地の荒廃や里山の景観の喪失といった環境保全への影響も心配されています。
近年は、水稲を中心にミニトマトやわさび・花きなどの施設栽培、特用林産物の栽培などが広く行われています。柿木村地区では地域ぐるみで有機農業に取り組んできた歴史があり、自給を中心とした有機栽培が広まっています。
よしかの林業
吉賀町の92%は山林が占めており、明治以降、松、杉、桧、ケヤキ、クリ等を用材として、ナラ、クヌギ、カシ、トチ等は薪用として利用してきました。また、同時期には製紙業における、楮(こうぞ)の生産も盛んに行われており、燃料としての利用では、昭和30年代には木炭の品評会も開催され、品質、生産技術の向上に町を挙げて取り組んだ経緯があり、里山の暮らしが営まれていました。
その後、昭和40年代に全国的に行われた拡大造林期を迎え、町内においても杉・桧・松の植栽が盛んに行われ、現在の森林形成率(人工林30%、天然性林70%)を構成しており、現在利用期に差し掛かっております。
吉賀町では平成25年度より、「木の駅プロジェクト」に取り組んでおり、出荷された木材に対して地域通貨券を発行し、森林の保全と地域商店の活性化に取り組んでいます。事業開始2年目の実績として、年間200㎥の木材が町内から集まっており、資源の地域内循環を目指す上で重要な役割を担っています。
また、平成27年度からは、森林を活用した取り組みを後押しする事業として、「吉賀町林業従事者育成事業」を開始し、チェンソーの技術指導や木材の搬出方法の指導を年間を通して行っています。この事業を活用し、今後、自伐型林業に移行する方や、原木椎茸の栽培者等の増加による、森林の幅広い活用を目指しています。